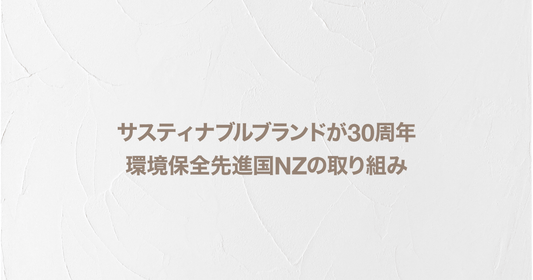今回ご紹介するワイン映画は、2018年のフランス映画「おかえり、ブルゴーニュへ」です。
前回ご紹介した「ブルゴーニュで会いましょう」に続き、舞台はフランスのブルゴーニュ。そして主人公がワイナリーを継ぐが否か悩む、という導入部分も似ていますが、実際に描いているテーマは違います。
ワイナリーの数だけストーリーがある。ということですね。
おお、なんだか名言っぽい…。

引用元:Amazon
ブルゴーニュのワイナリーに生まれた三兄妹。後継ぎとなるために幼少期からぶどうやワインについて父親から教えられてきましたが、長男のジャンは広い世界を見たいという気持ちから、放浪の旅に出てしまいます。
10年もの間ブルゴーニュから離れていたジャンですが、父親の危篤を知り、故郷へ帰ってきます。
しかし、4年前の母親の葬式にも参列せず音信不通だった兄に対して、妹・ジュリエットと弟・ジェレミーには少なからず不満がつのっていました。
ジャンはぶどうの収穫を手伝いながら兄弟の関係を少しずつ修復していきますが、間もなく父親が亡くなり、今度は莫大な相続税の問題が降りかかってきます。
ぶどう畑とワイナリーを含めた相続税はとても払いきれない金額だったため、その土地全て、もしくは畑の一部を売却するしかないという事態に。
代々受け継いできた大切なワイナリーを手放したくないという想いで3人は奮闘しますが、そのなかで各々が抱えてきた悩みも浮き彫りになっていきます。
3人はワイナリーを受け継ぐことができるのか、それとも手放すのか。
そして、ジャンはブルゴーニュに残ることを選ぶのか…。
若きワインのつくり手たちが、家族と自分の人生と向き合い奔走する、ワインへの情熱と家族愛を描いた作品です。
【この記事の登場人物】

-
みかさん
アパレル会社に勤務する35歳。ワインにハマり始めてる今、ワイングラスが気になってしょうがない。

-
岩須
このサイトの監修を担当する、ソムリエ。自身が名古屋で営むバーでは、ニュージーランドワインを豊富に取り揃える。
「おかえり、ブルゴーニュへ」詳細情報
| 映画ジャンル | ドラマ |
| テーマ | ワインづくり、家族、親子 |
| 原題 | Ce qui nous lie |
| 制作年/国 | 2018年/フランス |
| 時間 | 113分 |
| 監督 | セドリック・クラピッシュ |
| 脚本 | セドリック・クラピッシュ |
| 出演 |
・ピオ・マルマイ 「間奏曲はパリで」(2013年)等に出演。 2018年に主演した映画「トラブル・ウィズ・ユー」では フランスの映画賞セザール賞 主演男優賞にノミネートされるなど 今後の活躍も期待される俳優。 ・アナ・ジラルド 「FOUJITA」(2015年)等に出演。 父親はフランスの有名俳優、イポリット・ジラルド。 ・フランソワ・シビル 2016年の人気ドラマへの出演をきっかけに注目を集め始め、 2019年には3本もの映画で主演を務めるなど活躍中。 |
有名フランス人監督が手掛ける
監督のセドリック・クラピッシュ氏は日本でも人気のフランス人監督。
代表作「猫が行方不明」の他、「スパニッシュ・アパートメント」(2002年)、「ロシアン・ドールズ」(2005年)、「ニューヨークの巴里夫」(2013年)の3作は「青春三部作」と呼ばれ、高い評価を得てきました。
青春映画が得意な監督だけあって、本作もワイナリーの相続で悩む若者達の姿や、ぶどう畑で働く人々の活気を、豊かな表現力で描いています。
本物のワイン醸造家が出演
主人公たちのワイナリーで働くベテランワインメーカー・マルセル役を演じるのは、ジャン=マルク・ルーロ氏。
彼の本業は、ブルゴーニュで「ドメーヌ・ルーロ」を経営する、本物のワイン醸造家なんです。
一部のシーンは実際に、ドメーヌ・ルーロのワイナリーで行われたとのこと。
ワインに関するシーンにはルーロ氏の監修が入ったことで、世界中のワインファンに広く受け入れられる作品となりました。
原題の意味
原題の「Ce qui nous lie」は、Google翻訳にそのまま入力すると「私たちを束縛するもの」となりますが、このままだと少しネガティブなニュアンスに…。
ここでの「lie」は「〜を結びつける」という意味があるので、「私たちを結びつけるもの」と訳す方が、この作品には合うかもしれません。
そして「lie」はワイン用語の「sur lie(シュール・リー)」の「lie」(ワイン中の固形物:澱(おり))でもあります。
タイトルとワイン用語をかけてるんですね!お洒落!
「おかえり、ブルゴーニュへ」を見た感想
この作品を見て、最も強く思ったことは「気持ちは言葉にしなければ伝わらない」ということ。
劇中では様々なすれ違いや、言葉が足りなかったせいで酷い軋轢(あつれき)が生まれていたことに気付くというシーンが何度も出てきます。
そんなことで誤解し合っていたの?というシーンがいくつもあって、とても歯がゆさを感じました。と同時に、自分にも心当たりがあるな…とも思いました。
ワインのつくり手としての苦悩だけでなく、等身大の青年たちの悩みや葛藤が、みずみずしく描かれていましたね。
そして、残された三兄弟だけの物語かと思いきや、途中からジャンの妻(夫婦喧嘩中)と子供がオーストラリアからやって来たり、ジェレミーが婿入りした先の家族との問題が浮き上がってきたりと、相続問題ばかりではない、様々なテーマが絡み合っていきます。
それらはワイナリーに生まれた者として特別なことばかりではなく、誰もが人生で経験しうる身近な問題もあるので、共感を得ることができるんです。
共感するシーンがたくさんで…実は3回も泣いちゃいました!
もちろん、人間関係をしっかりと描き尽くすと同時に、ワインづくりの工程も時系列に沿ってしっかりと見せてくれます。
ぶどうの栽培から収穫、ワインの醸造まで、ワインができるまでの様々な過程を垣間見ることができるので、ワイン好きにはぜひ見て頂きたいですね。
私でもそんなに難しく感じることはありませんでした。活気溢れる収穫時期のシーンが印象に残ってます!
「ワインづくりは大変だ!」という苦労シーンばかりでなく、楽しいシーンや喜ばしいシーン、「こんなふうに作るんだ」と感心するようなシーンが盛りだくさん。
様々な面からワインの魅力を感じられる作品です。
ちなみに、この記事の冒頭で触れた「ブルゴーニュで会いましょう」との比較ですが、同じくフランス映画で、ワイナリー家族の物語ということで、似た印象なのは確かです。
しかし、描いているテーマは似て非なるもの。
ネタバレなしの範囲で敢えて言っておきたいことといえば、「おかえり、ブルゴーニュへ」の方が全体的に明るい雰囲気で、例えワインを飲んだことがない方でも楽しめるような雰囲気に仕上がっています。
これは監督が青春映画を得意とする方だからだと思います。
泣けるシーンから思わず笑ってしまうシーンまであり、非常にテンポが良く、約2時間があっという間。
ぜひ実際に見比べてみてください。
ブルゴーニュのワイン用語

(ブロゴーニュのワイナリー「ピエールクロ」の建物と畑)
「おかえり、ブルゴーニュへ」に登場するワイン用語を、わかりやすくまとめました。
割と難しい用語がサラッと出てくることもあるので、先に知っておくと、より楽しめると思います♪
キュヴェ
もともとは、ワインを発酵させる樽やタンクのこと。
今では、その樽に入ったワインそのもののことをそう呼んだり、それぞれのワインを区別するために名付けられたり、「他とは違う特別なワイン」という意味で使われたりします。
劇中では、近隣のワイナリーに婿入りした弟が、そこのワイナリーで自分が任されて作ったワインのことを「僕のキュヴェ」と呼んでいます。
この場合は「僕が作ったワイン」というニュアンスとなるでしょう。
澱引き(おりひき)
ワインの製造工程の1つ。 発酵が終わったワインの中の澱(おり)と呼ばれる沈殿物を、きれいな上澄みの部分から取り除く(引く)作業のことです。
除梗(じょこう)
ぶどうの房から渋みや苦みのある果梗(かこう)、つまりぶどうのヘタや柄の部分を取り除くことです。 この部分を適度に残すことで、ワインの味わいに変化をもたらすことができます。
ビオディナミ農法
有機栽培の農法の中でも最も厳格な農法。 農薬や化学肥料を使わないのはもちろんのこと、「宇宙の力を作物の栽培に活かしていく」という考え方のもと、独特のルールがあることで知られています。
マロラクティック発酵
通常のアルコール発酵の後、出来上がったワインの中のリンゴ酸が、乳酸菌の働きによって乳酸に変わる現象を言います。 この発酵が行われることにより、ワインの酸味がまろやかになり優しい印象の味わいになります。
まとめ
「おかえり、ブルゴーニュへ」は、ブルゴーニュのワイナリーに生まれた兄妹3人の成長とワインへの愛、そして家族愛を描いた、様々な要素が絡み合う充実したヒューマンドラマです。 ぶどうの栽培からワインの完成までの過程もじっくり見ることができるので、ワイン好きな方は特に興味をそそられることでしょう。
ワイン初心者さんでも、興味を持ってもらうきっかけになるような作品だと思います。
映画「おかえり、ブルゴーニュへ」を配信している動画配信サービスを調べるには、こちらのサイトが便利です。
当サイトでレビューした15本の映画記事をまとめました。こちらもぜひ御覧ください!